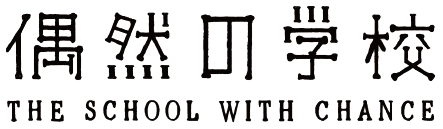わたしの祖母は今年で95歳になる。
幼い頃、祖母は生まれた時からずっとおばあちゃんとして生きているのだと思っていた。
父のことも母のことも同じように、当時のわたしの目に映る姿かたちと立場のまま、おかあさん、おとうさんとして生きているのだと思っていた。祖母にも産まれたばかりの赤ん坊だった頃があり、幼児から少女の時代も、若い母親だった時も中年のおばさんだった時もあったのだと知ったのは、もう少し成長してからのことだった。
わたしが物心ついた頃から、祖母は働く両親に代わってほとんどの家事や習い事の送り迎えを担当していた。平日の夕食はいつも祖母とわたしと妹で先に食べており、作ってくれるごはんはどれも美味しく、家に帰るのが楽しみだったのを覚えている。
以下は、祖母を表す好きなエピソード「食卓からみそ汁が消えた話」である。
まず私の家系は皆揃って呑兵衛だ。
家にはまずビール、それから4ℓ入りの甲類焼酎、芋焼酎や日本酒、ウイスキーにワインやジンまで様々な種類の酒が日常の中にあった。ある時、暗い流しの下を開けたら、沖縄土産の蛇がまるまる入ったハブ酒や高麗人参を漬けた薬酒など、理科室で目にする標本のような酒瓶が出てきて唖然としたこともある。
祖母は、慶応生まれの厳格な曾祖父母の躾のもと何事にも規則正しい性格をしているが、酒呑みの御多分に漏れずなかなか「いける口」の人でもある。現在も毎晩変わらず、コップにきっちり半分注いだ焼酎をお茶で割ったものを呑みながら夕食を摂るのが日課だ。
ある日祖母は、わたしと妹を呼んで淡々と告げた。
「あなた達は、もうじゅうぶん大きく育ったね。おばあちゃん、ふたりの栄養を思っておみそ汁作ってたけど、ごはんの時はお酒があるから欲しくないのね。これからは無くてもいい?」
大人になった今ならわかる。焼酎のお茶割りとみそ汁は一緒に飲むものではない。
その日からみそ汁が夕食に上ることはなくなったが、どうしても飲みたければ自分で作ればよいのだ。何も問題はなかった。ただそのことを宣言してから辞める、祖母の生真面目さとその理由のギャップがおかしかった。

祖母とは幾度も口喧嘩をした。
大体、わたしがいい加減な口答えをしたとか、片付けをしなかったとか、そのような発端だったと思う。その時腹立ちまぎれに祖母が言ったのは、わたしを「かわいい孫」だと思って気を許しているが、立場が違えばどうなのか考えてみろということだった。
本音のこぼれた一言に、ふと考えた。
祖母とわたしからいまの関係をはずし、違う立場で出会っていたら?
同じ家族でも、母と娘、または姉妹。もっと遠く、職場の上司と部下など。年齢や立場を様々に、頭の中で組み合わせてみた。祖母は生真面目かつ、こうと決めたら譲らない頑固な性格でもある。何事にもだらしない私の性格とは、「かわいい孫」のフィルターをはずしてしまうと実は相性が難しそうだ。上司と部下はもってのほか、母娘や姉妹でも距離が近すぎて危険だろう。もう少し考えてみる・・・例えば、同じ学校の同級生として出会っていたら?

祖母の漏らす思い出話のなかで強く印象に残っている話がある。
それは第二次世界大戦の始まる前のこと。少女時代の祖母は、当時華やかなレビューで浅草を彩った少女歌劇と呼ばれる松竹歌劇団(※1)に夢中だった。
なかでもひと際ファンであった劇団員の退団時には、彼女が故郷に帰る汽車のホームまで、物資の少ない中でこしらえた手土産を携えて友人たちと泣きながら見送りに行ったそうだ。
そんな祖母と同じく、わたしもきらきら美しい歌と踊りが大好きだ。いつか写真で見た、あどけないおさげ髪の祖母と一緒にはしゃぐ姿を想像してみる。もし同じ時代に生まれていたら、一緒にスタアの追っかけをしたのだろうか…。
なんて、過ぎた日の祖母に思いを馳せてみる。それから、今を生きる祖母に視線を戻す。
ひとに歴史あり——と言うが、考えてみればわたしは祖母の人生の大半を知らない。
しかし、祖母に会って話すとき、ふとした瞬間に、様々な時代の知らない祖母が透けて見える気がするのだ。曾祖父母の娘の顔、祖父の生涯を共にした妻の顔、父を育てた母の顔、職場の同僚や隣の住人や誰かの大切な友達と過ごす顔。
誰かを愛したことや憎んだこと、またその逆も然り、祖母の過ごしたそれぞれの時間が、深く編まれた織物のようにいまの祖母を構成しているように感じる。
平成が終わろうとしている現在、祖母はにこにこ笑って、今が一番楽しいのだと言う。
それは、変化を受け入れ、時代の移り変わりと共に様々な立場を生きた祖母の強さの証でもあった。皺が滲む目尻にすがすがしさを含んで、彼女は今日も笑っている。

※1 宝塚少女歌劇団に始まる日本の少女歌劇団の系譜に属するミュージカル及びレビューを行う劇団。1928年に松竹を母体とし発足、東京・浅草に本拠を置いていた。